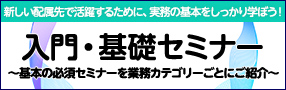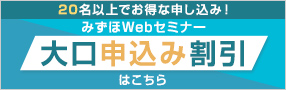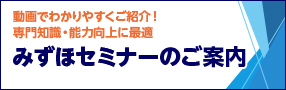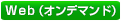
<2025年6月改正法成立>必須のカスハラ対策まで徹底解説!
ハラスメント相談窓口の最新対応実務(9/1~10/8配信)
具体的なヒアリング手順、窓口担当者向けの研修・マニュアル作成など、最新事例をふまえた25ポイント
セミナーNo.25-10966
厚労省指針では、企業におけるハラスメント防止措置の一つとして、相談窓口の設置が義務付けられていますが、これはただ単に相談窓口を設置するだけでなく、相談窓口担当者の「適切な対応」のために、研修やマニュアル作成に取り組むことまでが求められています。また、2025年6月に成立した改正法により、カスハラや就活セクハラに対しても対策が義務化されたことで、現行体制の見直しが急務となりました。 本セミナーでは、ヒアリングの手順や事実認定など、窓口担当者が必ず押さえておきたい実務のポイントから、マタハラ・ケアハラ・SOGIハラ等の多様化するハラスメントの基本知識、改正法で新たに義務化されたハラスメント対策まで、実務の悩みポイントを踏まえ徹底的に解説します。
≪窓口担当者向けの社内研修としてもご活用いただけます≫
| 対象 | 経営者、人事・労務、法務ご担当、管理者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
申込期間 配信期間 |
<申込期間>2025年9月22日(月)まで ※受講料入金期限:2025年9月25日(木) <配信期間>2025年9月1日(月)~2025年10月8日(水) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約220分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
|||||||||
| 受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- 【基礎知識の確認】
- 1 相談窓口対応は法律上の義務という意識
- 2 窓口担当者が適切に対応するための仕組み(研修・マニュアル等)
- 【初動対応と面談セッティングまでのポイント】
- 3 相談者に接する態度・スタンス
- 4 初回面談時の流れ・フロー
- 5 時間、場所のセッティング
- 【ヒアリングのポイント】
- 6 行為者・第三者ヒアリングでの確認ポイント
- 7 行為者ヒアリング時に必ず伝えるべき事項
- 8 行為者を「自宅待機」にしてもよいか
- 9 第三者ヒアリングのタイミングはいつがよいか?
- *窓口担当者向けマニュアル作りのポイント<サンプル進呈>
- 【相談窓口対応の悩みポイント】
- 10 相談者が「調査しないでほしい」と述べた場合の対応
- 11 「指導目的だった」「業務上必要な指導だった」という弁明
- 12 パワハラの「線引き」についてどう考えるか?
- 13 どう調査しても真偽不明に陥った場合
- 【事実認定の手法】
- 14 供述の信用性判断と事実認定の手法
- 15 事例①:1対1の面談で暴言・怒鳴り声を受けたとの訴え
- 16 事例②:きつい言い方・責める口調で複数の部下が疲弊
- 【多様化するハラスメントと正しい理解】
- 17 明確なパワハラ言動はないが部下を病ませる上司(本当のパワハラ問題)
- 18 不同意わいせつはセクハラではない
- 19 性別役割分担意識に基づく言動(ジェンダーハラスメント)
- 20 マタハラ・パタハラ・ケアハラ(育児・介護とハラスメント)
- 21 SOGIハラ(性的指向・性自認とハラスメント)
- 【改正法により新たに義務化されたハラスメント対策】
- 22 2025年6月成立!カスハラ防止と就活セクハラの改正法
- 23 法改正により企業に義務付けられる内容
- 24 カスハラ言動、就活セクハラの具体例として何が挙げられるか
- 25 企業のカスハラ防止策は「従業員を守る」だけでよいのか?
- <ハラスメントに関する裁判例解説>
- ① 職場の人間関係を調整して孤立しないようにする義務 - 東京高裁令5.6.28
- ② ハラスメント委員会による対応は相当だったか - 東京高裁令4.10.24判決
- ③ 顧客へのハラスメントを理由に懲戒処分 - 最高裁平30.11.16判決
- ④ その人に向かってではない間接的な言動もパワハラに - 東京高裁平29.10.18判決
- ⑤ 厳しい指導も業務上の指示の範囲内 - 東京地裁平21.10.25判決
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。