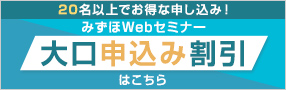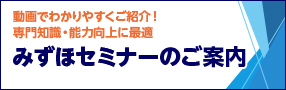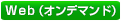
コーポレート・ガバナンス強化とリスク多様化の時代に対応!
『全社的リスクマネジメント(ERM)』の構築と運用の実務
(6/16~7/8配信)
体制整備からPDCAによる実効性確保、危機管理・BCPの基本までをわかりやすく解説
セミナーNo.25-10658
企業を取り巻くリスクが年々多様化・複雑化している今、従来の各部門任せの対応には限界があり、グループ会社を含めたリスク情報を全社で把握・集約し、効率的・効果的に対応する体制づくり、いわゆる「全社的リスクマネジメント(ERM)」の構築が求められます。会社法、金融商品取引法などの法制度の観点から、既に体制や規程を整えている企業も増えていますが、実効性ある運用やPDCAの定着、体制の高度化といった面で課題を抱える企業も少なくありません。
本セミナーでは、ERMに初めて取り組む方でも安心して学べるように、基礎的な考え方から丁寧に解説するとともに、すでに一定の体制を築いている実務者に向けて、実効性ある運用や体制の高度化に向けて、考慮すべき視点や取組の方向性を分かり易く解説します。また、危機管理マニュアルの整備や事業継続計画(BCP)の策定といった危機対応の基本も取り上げ、実効性ある体制づくりに向けた具体策をご紹介します。
≪体制構築・見直しの実務にすぐにご活用いただけるリスク管理規程・危機管理規程のサンプル資料を配布≫
| 対象 | 経営企画・リスク管理・内部統制・内部監査・CSR担当幹部・スタッフ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
申込期間 配信期間 |
<申込期間>2025年6月23日(月)まで ※受講料入金期限:2025年6月25日(水) <配信期間>2025年6月16日(月)~2025年7月8日(火) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間約330分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
|||||||||
| 受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師

コントロールソリューションズ㈱
代表取締役社長
公認会計士
佐々野 未知 氏
略歴
上智大学経済学部卒業。大原簿記学校講師、青山監査法人(当時)勤務を経て、1998年KPMGニューヨーク事務所に入社。2002年以降は、KPMG東京事務所(現あずさ監査法人)にて外資系企業の法定監査、デューデリジェンス、SOX法対応支援業務を担当する。現在は、経営コンサルタントとして、内部統制構築支援やIFRSコンバージョン支援に携わるとともに、各種実務セミナー講師としても活躍中。豊かな経験に最新の情報もふまえ、随所に事例・設例を織り込んだ実務本位の明快な指導には定評がある。
主著
「フローチャート式ですぐに使える 内部統制の入門と実践(第2版)」「内部統制の評価・活用ノウハウ ムリ・ムダ・ムラをなくしてIFRSs、ERMへ展開」(いずれも中央経済社)ほか多数。
講義内容
- 1.企業を取り巻くリスクと全社的リスクマネジメント(ERM)の必要性
- (1)企業の成長と増大するリスクとERMの必要性、内部統制との関係
- (2)リスクマネジメントの国際的枠組み(ISO 31000、COSO ERMフレームワーク)
- (3)関連法令・制度(会社法、金融商品取引法、有価証券報告書、CGコード等)
- (4)サステナビリティ対応やESGとの関係
- (5)危機管理との違いと役割分担
- 2.リスクマネジメントの体制づくりと基本方針
- (1)PDCAに基づくリスクマネジメント体制の全体像
- (2)リスクマネジメントを担う組織と責任体制(役割・関係部門との連携)
- (3)リスクの定義、マネジメントの目的と範囲
- (4)基本方針策定のポイントとトップマネジメントの関与
- (5)リスク管理規程の整備、参考事例の紹介
- 3.リスクの特定・評価と対応策の設計
- (1)リスクの洗い出し手法と網羅性の確保
- (2)リスクの分類の体系化(戦略・財務・オペレーション・コンプライアンス等)
- (3)リスク評価:影響度×発生可能性による分析とマトリクスの活用
- (4)リスク選定基準とリスク選好(リスクアペタイト)との整合性
- (5)対応策の立案と文書化(回避・低減・移転・受容)
- 4.リスクマネジメントの運用と継続的改善
- (1)リスクマネジメントプログラムの策定と実行計画
- (2)モニタリングの設計:実施主体、頻度、連携体制
- (3)モニタリングの視点と評価項目(KRIなど)
- (4)定期的な見直しと重要リスク・対応策のアップデート
- (5)取締役会等へのリスク報告の在り方
- 5.危機管理と事業継続計画(BCP)による対応力強化
- (1)顕在化したリスクへの対応:危機管理とERMの補完関係
- (2)危機管理体制の構築:対策本部・指揮命令・エスカレーションルールの整備
- (3)危機管理規程の整備、参考事例の紹介
- (4)事業継続計画(BCP)の基礎と昨今の動向(災害・感染症・サイバー対応など)
- (5)BCP策定の手順と社内訓練の重要性
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。